「この敵、どうやって倒せばいいのかな?」
小学4年の娘が、そんなひと言をつぶやきました。
マインクラフトの中で、ゾンビに囲まれてピンチの場面。
昔なら、YouTubeで攻略動画を探していたかもしれません。
でも、今の子どもはちょっと違います。
スマホで画面をパシャッと撮って、ChatGPTに質問。
「罠を作っておびき寄せるのがいいって!」
そう言って、友だちとチャットしながら罠づくりをはじめました。
その様子を見ながら私は思いました。
もう“ググる”時代じゃないんだな。
そして“考える力”の育ち方も、すごく変わってきてるなって。
↓↓ 要約動画(1分43秒)↓↓
「検索する」から「聞く」へ
昔は、「わからないことがあったら調べようね」が合言葉でした。
でも今は、ChatGPTみたいなAIに聞けば、あっという間に答えが返ってきます。
たとえば、英語の説明もスマホで撮ってGPTにかければ、だいたいの意味がわかります。
そのかわり、「どう聞くか?」が大事になってきました。
つまり、「調べる力」よりも、「聞き方」「考え方」の力が、今の時代に必要なんです。
マイクラは“考える力”のトレーニング
マイクラって、自由すぎるくらい自由なゲーム。
「どこに拠点をつくる?」「どうやって敵をよける?」「どのアイテムを集める?」
そういうのを、ぜんぶ自分で考えないといけません。
友だちと同じワールドで協力したり、役わりを決めて冒険したりすることもできます。
しかも、「〇〇の装置ってどう作るの?」とGPTに聞けば、アドバイスまでくれる。
現実ではむずかしい「協力」や「戦略づくり」も、ゲームの中なら気軽にできるんです。
あわせて読みたい:【マイクラ映画レビュー】ゲーム・体験・映画がつながる!“想像力”と“学び”のヒント
プログラミングとそっくりな遊び方
マイクラの中には、「レッドストーン」っていう仕組みがあります。
これを使うと、自動でドアが開いたり、敵を感知してトラップが動いたりします。
じつはこれ、考え方がプログラミングとそっくり。
「どう動いてほしいか」を決めて、それに合わせてブロックを組んでいくんです。
しかも、失敗してもすぐ作り直せる。
わからなければGPTがヒントをくれる。
だから、自然と「作る力」「考える力」がどんどん育ちます。

失敗しても、大丈夫
マイクラって、うまくいかないことがたくさんあります。
でもそれがいいんです。
たとえば、うちの子が「回路が動かない」と困っていたとき、GPTに「これ、どこが悪い?」って聞いていました。
すると、「信号が届いてないかも」「この位置を変えてみて」とアドバイスが返ってきた。
試してみたら、ちゃんと動いた!
こうして、「失敗⇒考える⇒なおす⇒成功!」というサイクルが、自然とまわっていきます。
あわせて読みたい:Scratch vs マインクラフト~初心者に最適なのはどっち?親目線で徹底比較!
自宅でも“考える力”は育てられる
こうした学びは、マイクラだけではありません。
家でできる教材やオンライン教室も、とっても充実しています。
▶ ワンダーボックス
遊びながら考える力を育てたいという方には、【ワンダーボックス】がおすすめです。
STEAM教育の考え方をベースに、タブレット上でパズルやアート、空間認識ゲームなどが遊べます。
マイクラ好きな子にもぴったりな“自分で考える”教材です。
話題のSTEAM・プログラミング教育教材なら【ワンダーボックス】
▶ アンズテック
”うちの子、もっと本格的にプログラミングを学びたいかも…”という方には、【アンズテック】というオンライン教室もあります。
マイクラやScratchを使ったレッスンで、考える力とプログラミングスキルを同時に伸ばせるのがポイント。
自宅で受けられるので、忙しいご家庭にも◎です。
小中学生専門のオンランプログラミングスクール【アンズテック】
おわりに:わからないことがこわくない子に
マイクラとGPT。
このふたつを使えば、「わからないこと=こわいこと」じゃなくなります。
子どもは自分のペースで考えて、試して、直して、また挑戦する。
それって、すごく大事な力。
プログラミングの知識がなくても、特別な塾に通わなくても、
家庭の中でも“考える力”はちゃんと育てられる。
これからの時代に必要なのは、「答えを知っている子」じゃなくて、「考え続けられる子」。
そんな子に育ってほしいなと思います。
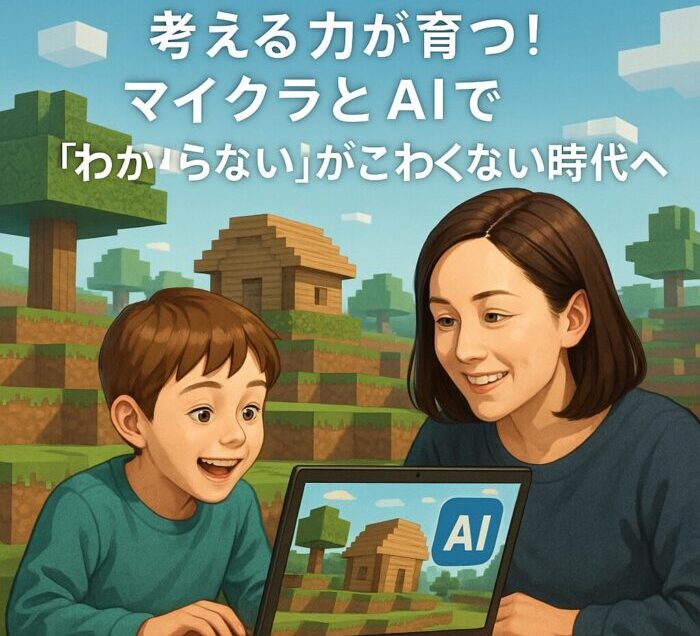


コメント