『複利』と聞いて、多くの人はお金を思い浮かべます。
たしかに、時間を味方につけて資産を膨らませていく複利の力は、投資の世界では常識中の常識。
しかし、実はこの『複利』という考え方は、お金だけに限った話ではありません。
もっとも大きなリターンを生む複利投資は、教育です。
とくに子どもにとって、日々のちょっとした学びや経験の積み重ねが、将来にとてつもない差を生む可能性を秘めています。
↓↓ 要約動画(2分5秒)↓↓
複利とは「成長が成長を生む仕組み」
まず、複利の本質を簡単におさらいしておきましょう。
『 複利=成果が再び成果を生むサイクル 』
たとえば100万円を年5%で運用すると、1年後は105万円に。次の年は、この105万円に5%がかかるため、増える額が少しずつ大きくなっていきます。
この「時間が経つほど加速度的に差が広がっていく」という考え方は、お金だけでなく、知識・スキル・習慣にも当てはまります。
あわせて読みたい:中学受験 vs プログラミング:どちらが将来の武器になるのか?
偉人や成功者たちは「教育の複利」を信じていた
イチローの毎日同じルーティン
野球界のレジェンド、イチロー選手は「1日たりとも同じように見える日はない。すべてが違う」と語りました。
地味で地道な努力を、毎日続けてきたからこそ、あれほどの記録を打ち立てられたのです。
“たかが1日”を、積み重ねた人が人生を変える。まさに複利の精神です。
Google社員の「20%ルール」
Googleでは、社員が業務時間の20%を自由な研究や開発に使っていいというルールがあります。
この“自由な余白”から生まれたのが、GmailやGoogle Mapsといった世界的サービスです。
会社として、「目に見えない学びや挑戦が、やがて大きな成果に育つ」という複利の本質を理解している証拠です。
教育は「金融資産よりも安定した複利」
相場は日々変動します。2025年4月現在、トランプ再選への懸念などで株式市場は大きく揺れています。(リンク:トランプ政策による暴落の記事)
一方、教育に投じた時間や習慣は、暴落しない“無形資産”として子どもに残ります。
金融資産の複利は増減しますが、教育の複利はブレずに積み上がるのです。
統計が示す「教育と将来」の明確な相関
教育の効果は、数字でもはっきり出ています。
OECDのデータでは、高等教育を受けた人はそうでない人に比べて生涯所得が約1.5倍以上という結果が出ています。
また、文部科学省の調査では、家庭内で読書や会話の多い子どもほど学力が高い傾向があり、非認知能力(やり抜く力、集中力など)にも差が出るとされています。
つまり、今すぐ成果が出なくても、教育の種は確実に未来で芽を出すということです。
あわせて読みたい:読解力とプログラミング的思考は矛盾する?国語軽視の流れを考える
子どもにとっての「複利の種」とは?
それは、決して難しい教材や高価な習い事ではありません。
- 絵本の読み聞かせ
- 「なんで?」を大切にする会話
- 毎日のちょっとした振り返りや褒め言葉
- 家計やお金の話をオープンにする
- 英語やプログラミングに少し触れてみる
こうした日常の中の教育こそが、もっとも複利の効く種になります。
毎日の小さな刺激が、知的好奇心・語彙力・自己肯定感をじわじわと育てるのです。
親こそが「複利の媒介者」
教育の複利を生むのは、学校でも塾でもなく、家庭です。
とくに共働き家庭では、時間的な制約がある分“何を積み上げるか”を選ぶ力が求められます。
親自身が学ぶ姿勢を見せれば、子どもも自然に真似します。
親が本を読めば、子も読みたくなり、親が節約や投資を意識すれば、子どもも“お金に強い子”に育ちます。
「教育は教えるものではなく、背中で見せるもの」―まさにそれが複利の源です。
教育の複利は、静かに、でも確実に効いてくる
教育における複利は、劇的な変化ではありません。
でも10年後、子どもが社会に出る頃には、「やってきた子」と「やってこなかった子」で、見える景色がまったく違うことになります。
そして、複利が効き出した瞬間からは“ほとんど努力しなくても自然に伸びるフェーズ”に入っていきます。
それこそが、教育における最強のリターンです。
自宅で育てる「考える力」──ワンダーボックス
思考力や創造性を、遊びながら伸ばせるのが「ワンダーボックス」。
STEAM教育に基づいた教材で、毎月届くキットとアプリで子どもが夢中になります。
共働き家庭でも、親の手をかけずに“学びの種まき”ができるのが魅力です。
話題のSTEAM・プログラミング教育教材なら【ワンダーボックス】 ![]()
論理的思考をマンツーマンで──Codeland(コードランド)
もっと本格的に学ばせたい方には「Codeland」。
小中高生向けのオンラインマンツーマンプログラミングスクールで、
プロ講師が一人ひとりに合わせて丁寧に指導してくれます。
今なら無料体験会も実施中。まずは気軽に試してみてください。
↓↓ Codelandリンク↓↓
今こそ「複利のポートフォリオ」を見直そう
株や不動産などの金融資産に目がいきがちな今こそ、「教育という目に見えない資産に、どれだけ種をまけているか?」という問いが重要になります。
教育の複利は、暴落しない。
そして、社会に出てから何十年も子どもを支えてくれる、一生モノの資産になります。
子どもが未来の階段を、自分の足で登っていけるように。
今日から始める「教育の複利投資」が、10年後にかけがえのない力になって返ってくるはずです。
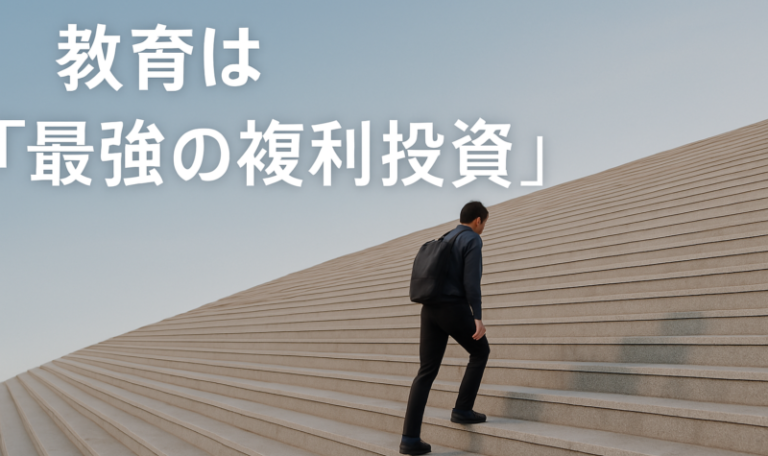
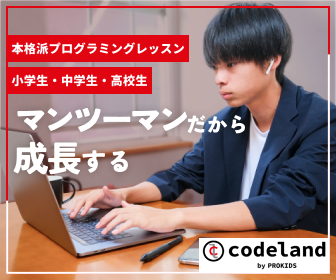

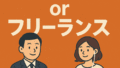
コメント