「AIって本当に学校でも教えるようになるの?」
そんなふうに思っていた方に、いよいよ現実になりそうなニュースが飛び込んできました。
2025年5月、文部科学省は中学校に“AIや情報を本格的に学ぶ新教科”を導入する方針を発表しました。
その名も「新・技術分野(仮称)」。2030年度から段階的に全国の中学校で導入される予定で、情報社会を生きる子どもたちに必要な知識とスキルを身につけさせるためのものです。
これは、単なるプログラミングの話ではありません。情報の扱い方、AIとの付き合い方、ネット社会のルールまで、これからの社会で“生き抜く力”を育てる教育へと変わっていくのです。
↓↓ 要約動画(2分20秒)↓↓
中学生が「AIの仕組み」を学ぶ時代に!
これまでの中学校では、「技術・家庭科」の一部として、ちょこっとだけ情報やプログラミングに触れる程度でした。でもこれからは違います。
2023年の学習指導要領改訂案では、以下のような内容が本格的に導入される予定です。
- 情報の集め方、まとめ方
- ネット社会の仕組みやルール
- 情報セキュリティの考え方
- AI(人工知能)の基本原理
- 簡単なプログラムの作成と活用
しかも、これらが“選択”ではなく“教科”としてしっかり学ばれるようになるのです。
あわせて読みたい:ChatGPTを使う子 vs 使わない子:未来の差はここで決まる
小学生にも影響がある?
はい、あります。小学校でも3〜6年生の「総合的な学習の時間」において、情報教育がカリキュラムとして正式に組み込まれる予定です。
たとえば次のようなことが授業で扱われます:
- 情報の正しい集め方
- データの簡単な整理や比較
- ネット上の危険とその対策
- AIや機械学習の簡単な考え方
つまり、小学生のうちから「デジタル社会にふさわしい考え方や使い方」を自然と身につけることが求められる時代になっていくということです。
早く始めるほど、差がつく時代に
プログラミングやAIに対する親和性(なじみやすさ)は、やはり早く始めるほど高くなります。
いきなり中学で「はい、AIとは?」と言われても、苦手意識が先に出てしまう子も多いかもしれません。
でも、ゲーム感覚で遊びながらプログラミングを体験できる教材が今はたくさんあります。家庭でのちょっとした取り組みが、将来の大きな自信になるはずです。
【おすすめ①】ゲームみたいに学べる「QUREO(キュレオ)」
小学生から中学生まで、幅広く対応!
ビジュアルプログラミングで遊び感覚なのに、内容はしっかり本格派。
教室型とオンライン型の両方が選べるので、ライフスタイルに合わせやすいのも魅力です。
↓↓公式サイトでチェック! ↓↓
教室数3,000以上!自宅の近くでプログラミングが学べる「QUREOプログラミング教室」
【おすすめ②】ヒューマンアカデミー ジュニア|本格派のプログラミング教室
全国に教室があり、通塾タイプでしっかり学びたい子向け。
ロボット制作やタイピング、プログラミングの基礎〜応用まで。
自宅学習コースもあり、場所を選ばず取り組めます。
↓↓公式サイトでチェック! ↓↓
累計10万人が学んだ【ロボット教室】
まとめ:親ができる“ちょっと先の準備”を
中学でAIを学ぶ時代が、いよいよすぐそこまで来ています。
でも焦る必要はありません。まずは、家庭でできることから一歩ずつ。興味を持つきっかけを与えてあげるだけで、子どもの意識はぐっと変わります。
我が家では母親の私がAI担当をしていますが、”ついに教育にもAIか・・・”と思う一方、あまりにも進化のスピードが速すぎて子供(小学4年生)がAIを学ぶころには、技術進化で先生がロボットになっているのではと思っています。(半分本気です)
だからこそ、情報を扱える力が「読み書き計算」に並ぶほど大事な基礎力になるかもしれません。
大きな変化が始まる今こそ、家庭でも「情報リテラシー」を意識していきたいですね。
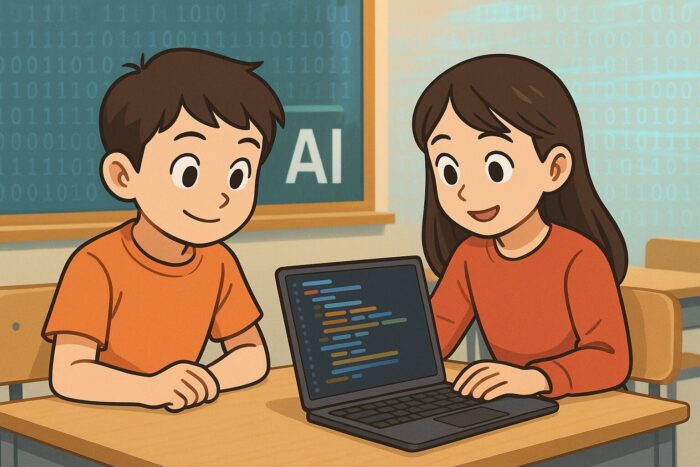


コメント