「これからは余暇をどう過ごすかの時代だよ」
ホリエモンが語ったそんな言葉に、未来の理想像を重ねる人もいるかもしれません。
けれど、それは“資産を持つ者”にだけ許された未来なのかもしれません。
現実は違います。
Googleでは既にエンジニアの25%がAIによるコード生成に関わっており、この比率は近い将来50%、さらには人間がほぼ介在しない開発体制へと向かう可能性も指摘されています。
これは、単なる効率化ではありません。「人がいらなくなる世界」への入り口です。
そしてそれは、静かにでも確実に、私たちの生活にも影響を与え始めています。
↓↓ 要約動画(2分24秒)↓↓
AIに奪われるのは“仕事”だけではない
「AIが仕事を奪う」と聞くと、多くの人は工場労働や事務職などを思い浮かべます。
しかし今、AIが置き換えているのはプログラミング・マーケティング・企画、さらには医療や法律分野にまで及んでいます。
しかもそれは、24時間休まず、安定して作業できる“無限労働力”。
当然、人件費の削減とリストラはセットです。
未来が「仕事がなくなる」ではなく、「一部の人にしか仕事が回らなくなる」社会だとしたら。
そしてそれが現実になりつつある今・・・
あわせて読みたい:AIが仕事を奪うのではない。AIを使う人間が、あなたの仕事を奪う時代
“余暇”は一部の人間の特権になる
「AIが働いてくれるから、あとは余暇を楽しめばいいじゃん」というのは、資産がある側の人間だけの話です。
大多数の人にとって、AIの浸透は「仕事の消滅」ではなく「低単価労働の拡大」や「副業・複業の強制化」につながります。
余暇どころか、“貧乏暇なし”の状態がさらに深刻化するのです。
ホワイトカラー職がAIに代替され、ブルーカラーは人手不足のまま放置される。
そんな“二極化社会”が今、着実に進行しています。
あわせて読みたい:ホワイトもブルーも関係ない時代に必要なIT軸の教育とは? 〜職種を越えるプログラミング的思考〜
日本から富が流出する未来
私たちは日々、Google検索、YouTube、Chrome、Gmail、そしてAIチャットを使っています。
これらのインフラはすべてアメリカ企業のものであり、そこで使われるのは“無料サービス”ではありません。
それは、私たちの「時間」「データ」「広告収入」、そして『日本円』です。
日本人がどれだけGoogle広告をクリックしても、YouTubeで動画を見ても、収益の大半は円からドルへと換金され、最終的にアメリカ企業の株主へと流れていきます。
“AI消費国”日本の未来は、使えば使うほど“搾取される構造”に陥る可能性があります。
それでも未来を選べる人へ
では、どうすればいいのか。 答えはシンプルです。
「AIを使う側」に回ること。
動画の作成や投稿を通じて情報を発信する。AIと組んで新しい何かを生み出す。
今はそのすべてが、スマホひとつでできる時代です。
なんとなく使うのではなく、戦略的にAIを使うことが稼げる人材につながります。
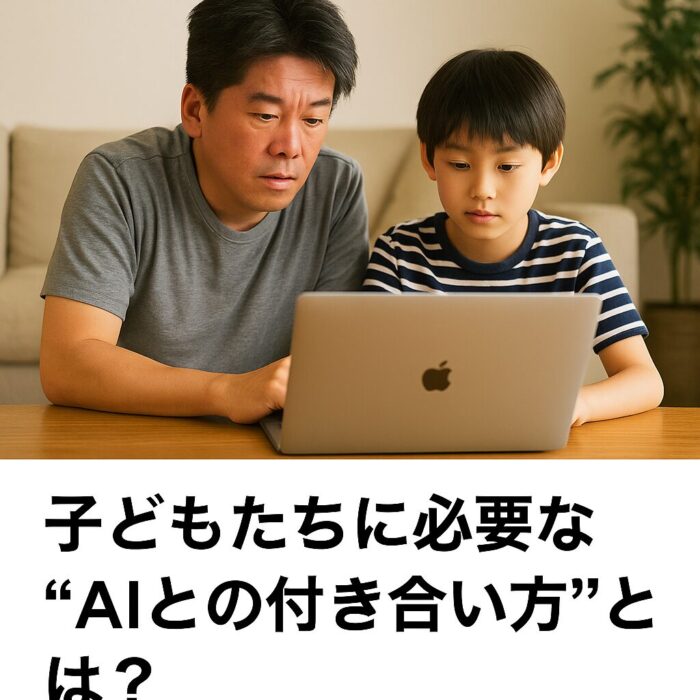
子どもたちに必要な“AIとの付き合い方”とは?
AI時代を生き抜く子どもたちにとって、単に使えるだけでは足りません。
重要なのは、「どう活かすか」です。
以下に具体的な取り組み例を紹介します:
- ScratchやQUREOでプログラミング的思考を育てる ⇒「繰り返し」「条件分岐」など、AIとの対話や構造理解の土台になる。
- ChatGPTと一緒に作文・物語・英語学習をさせる ⇒“AIとの対話”は、もはや新しい国語の時間。自然な思考と言語化力が育つ。
- YouTubeやブログで自分の考えを発信する体験を持たせる + 発信⇒価値創造。小さくても「届ける力」を育てれば、将来の仕事に直結する。
- AIを“道具”として自分の目標に使わせるマインドセットを教える ⇒「AIに任せる」ではなく「AIに働かせる」という感覚を早めに持たせる。
教室数3,000以上!自宅の近くでプログラミングが学べる「QUREOプログラミング教室」
親として、我が子に伝えたいこと
私自身、子ども2人に何度も伝えていることがあります。
「YouTubeを見るな」とは言いません。ですが、「目的をもって見る」「自分が何を得たいのかを考えて見る」ことだけは徹底してほしい。
昨日も、長男が朝早く起きたのにダラダラとショート動画を眺めている姿に、怒ってしまいました。
「その時間、未来の自分にとって意味がある?」「自分の意思で見ている?」
と問いかけたくなるのです。
こんな風にAI社会のことを書いている自分でも、我が子ひとり育てるのは本当に難しい。
でもふと、思い出しました。
自分の親が昔、「ファミコンばっかりするな」「テレビばかり見てるとバカになる」と言っていたあの言葉の意味。
今なら、少しだけわかる気がします・・・
情報の洪水の中で、子どもに“考える力”と“選ぶ目”をどう育てるか。
それこそが、AI時代の最大の親心なのかもしれません。
ユートピアになるか、ディストピアになるか
子どもたちにも必要なのは、英語力や受験偏差値ではなく、「AI×表現力」です。
ユートピアになるか、ディストピアになるか。
それは、今日の一歩が決めるのかもしれません。



コメント