「プログラミングって小学生からでいいんじゃない?」
「3歳なんて早すぎるでしょ?」
そう思っていませんか?でも、『3歳まで』こそが、子どもの脳の発達にとって最も重要な時期。
この時期に「遊び」を通じてプログラミング的思考を育むことは、将来の学びに大きな影響を与えることが、数々の研究でも示されています。
この記事では、そんな「3歳からのプログラミング教育」について、学術的な根拠も交えながら、分かりやすくご紹介していきます。
↓↓要約動画(2分46秒)↓↓
幼児教育は“3歳までがカギ”といわれる理由
「人間の脳の90%は、5歳までに完成する」とよく言われます。
特に3歳までの時期は、感情、記憶、思考を司る領域が急成長する“ゴールデンタイム”。
このことを裏づけるのが、以下の2つの有名な研究です。
ペリー就学前プログラム(アメリカ)
経済的に恵まれない3〜4歳の子どもたちに高品質な幼児教育を行ったところ、後の学力・収入・持ち家率・犯罪率などに明確な差が出たという研究。
→ 特に3歳から始めたグループで顕著な効果が確認されました。
アベセダリアンプロジェクト
こちらも生後数ヶ月から5歳までの幼児に手厚い教育を行った追跡研究で、大学進学率や収入、健康状態において大きな成果が見られました。
つまり、早すぎるのではなく、3歳からこそ価値があるのです。
そもそも「プログラミング的思考」って何?
3歳の子にプログラミングと聞くと、「パソコン?」「タイピング?」とイメージしがちですが、実際はそうではありません。
プログラミング的思考とは?
- 順序立てて考える
- 「もし〜なら〜する」という論理
- 目的達成のためのステップを考える
このように、日常の中でも自然と使っている考える力そのものなんです。
たとえば、「積み木でタワーを作る」⇒「崩れた」⇒「土台を広くしてみる」
これも立派なデバッグ(修正)であり、アルゴリズムの改善です。
3歳でもできる!遊びながら育つプログラミング思考
キュベット(Cubetto)
-
木製のロボットに、ブロックで指示を出して進ませるおもちゃ
-
画面を一切使わず“順序”や“ルール”を直感で理解できる
-
世界中の幼児教育現場で採用されている
くもんのロジカルルートパズル
-
ピースを並べて、ボールがゴールに届くルートを作る
-
試行錯誤・改善・原因の分析といった“プログラミング脳”を刺激
プログラミング絵本シリーズ
-
「もし、〇〇だったら?」という選択肢型の物語
-
小さな子でもストーリーを楽しみながら論理を体験できる
🧸 その他おすすめキーワード
-
知育タブレット
-
プログラミング カードゲーム 幼児
-
ボードゲーム プログラミング風
親が気になる“早期教育”のよくある疑問
本当に意味あるの?まだ遊んでるだけじゃ…
⇒はい、それでOKです!むしろ「遊びながら学ぶ」が最も効果的な学習方法です。
早すぎて嫌いになったらどうしよう…
⇒ 無理にさせる必要はありません。あくまで“選択肢としてのプログラミング遊び”を取り入れるくらいの気持ちでOKです。
親が詳しくないけど教えられる?
⇒ むしろ一緒に“初めて”を楽しめるチャンス!
解説動画やアプリも豊富にあるので、一緒に学びながらで大丈夫です。
実は兄姉と一緒にできる“年の差プログラミング”
3歳児が1人でできることは限られていますが、兄姉がスクラッチやマイクラで遊んでいる場合、「お手伝い係」として参加させることで自然に興味を持ちやすくなります。
- ブロックの色を並べてもらう
- コマンドカードを順番に並べてもらう
- 「ここ押してみて!」とお願いして一緒に体験する
⇒ 「わたしもできた!」という達成感がモチベーションになります。
3歳でもできる!遊びながら育つプログラミング思考
ワンダーボックス(WonderBox)
STEAM教育を取り入れた知育教材で、年少から対象。
デジタル×リアルの組み合わせで「論理力」や「創造力」が自然に育つ。
アプリだけでなく、工作・パズルなどのリアル教材も魅力。
話題のSTEAM・プログラミング教育教材なら【ワンダーボックス】 ![]()
LITALICOワンダー
年長~小学生向けの本格プログラミング教室。
「ロボット」「ゲーム」「3Dモデリング」などを通じて、個別最適な学びを提供。
お兄ちゃんお姉ちゃんが通っていれば、一緒に見学や体験もおすすめ。
子ども向けプログラミング・ロボット教室【LITALICOワンダー】 ![]()
まとめ:3歳からのプログラミング教育は「将来の土台」
- 幼児教育は3歳までが最も効果があることが研究で証明されている
- プログラミング教育は、論理的思考・問題解決力・創造性を育むカギ
- 無理に教える必要はなく、遊びや親子の関わりの中で自然と育てるのがベスト
「早すぎるかも…?」と思ったときこそチャンス。
まずは1つ、おもちゃや絵本を手に取って、一緒に遊んでみてください😊
我が家では子供が小中学生になっているので難しいですが、マイクラを通じてプログラミング的思考を鍛えようと思います…
あわせて読みたい:幼稚園児のプログラミングスクールで未来の可能性を広げよう

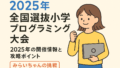

コメント