「今日はちゃんと宿題をしたらアイスね!」「100点取ったらSwitchの時間を30分延ばすよ」
こんなふうに“ごほうび”で子どものやる気を引き出した経験、きっとどの家庭にもありますよね。
目の前の行動を引き出すには、わかりやすく即効性のある方法です。
しかし一方で、「ごほうびがないとやらない子になってしまった」「ごほうびの内容がエスカレートして困っている」という声もよく聞かれます。
親としては、「どうすればやる気を保てるのか」「そもそもごほうびって使っていいの?」というモヤモヤを抱える場面も多いのではないでしょうか。
この記事では、ごほうびが子どもに与える影響、そして上手に使ってモチベーションを育てるためのコツを、教育心理学や教育経済学の考えも交えて紹介します。
後半では、わが家の“うまくいった(いかなかった)”実例もご紹介しています。
↓↓要約動画(2分51秒)↓↓
ごほうびはなぜ効くのか?「外発的動機づけ」の力
やる気の仕組みを理解するうえで欠かせないのが、「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」という考え方です。
内発的動機づけとは、「面白そうだからやってみたい」「もっと知りたいからやる」といった、自分の内側から生まれるやる気。
反対に外発的動機づけは、「ごほうびがもらえる」「怒られたくない」といった、外からの刺激で動くやる気です。
心理学者のエドワード・デシとリチャード・ライアンが提唱した「自己決定理論」によれば、人間のやる気を持続させるには、「自分で選びたい(自律性)」「できると感じたい(有能感)」「人とつながりたい(関係性)」といった欲求が満たされることが大切とされています。
特に小さな子どもにとっては、ごほうびによる外発的動機づけがわかりやすく、即効性もあります。たとえば、「10分Scratchに触ったらシールを1枚」などのごほうびは、「やってみようかな」というきっかけになります。
ただし、ここに落とし穴もあります。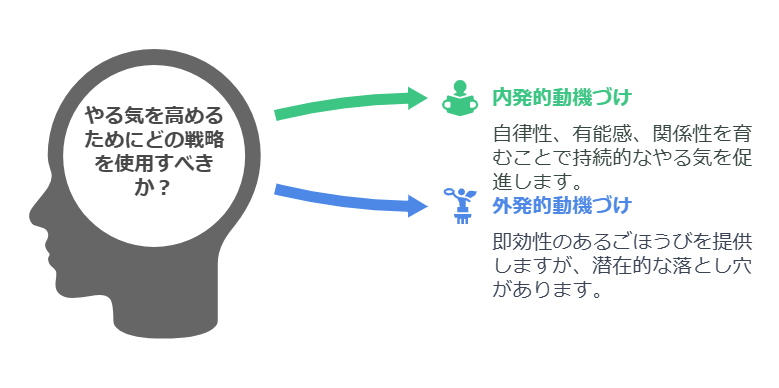
「アンダーマイニング効果」に要注意
もともと楽しんでいたことに報酬を与えると、その報酬がなくなったときにやる気まで失われる― この現象は「アンダーマイニング効果」と呼ばれています。
デシの有名な実験では、大学生にパズルを解かせるという課題を与え、途中から報酬を与えるようにしました。すると、報酬を受け取ったグループは、報酬がなくなった後には興味を失い、取り組み時間が大幅に減少したのです。
このことからも、ごほうびは強力なツールである一方、「やる意味」がごほうびだけになってしまうと、本来の目的が見失われてしまうことが分かります。
ごほうびでやりがちなNG例
効果的なごほうび活用のためには、ありがちなNGパターンを知っておくことも重要です。
-
物で釣るようなごほうび
「Switch買ってあげるからテスト頑張って」など、モノを与えるごほうびは、一時的に強い動機づけになりますが、続かないどころかエスカレートしがちです。 -
毎回条件反射のように与える
宿題をしたら毎回シール、言われたことを守ったら毎回アイス…と「やったら必ずもらえる」が常態化すると、ごほうびが前提になり、自主性が失われます。 -
比較を伴うごほうび
「○○ちゃんより成績がよかったら買ってあげる」など、他者との比較が絡むと、健全な競争ではなく、自己肯定感の低下や嫉妬につながることもあります。
上手なごほうびの与え方5つのコツ
では、どのようにごほうびを使えば、子どものモチベーションを支えることができるのでしょうか?ポイントは“あくまで一時的なサポート”として活用することです。
-
ごほうびは「成長」に紐づける
ごほうびの基準は、「結果」ではなく「過程」に。たとえば「10分集中して問題を解いたらOK」など、努力に焦点を当てたごほうびが有効です。 -
「頑張った過程」に注目する
「100点取れてえらいね」よりも「毎日コツコツ復習してたからだね」と声をかけると、努力すること自体の価値が伝わります。 -
段階的にステップアップする
最初は目に見えるごほうびでもOKですが、徐々に「親の言葉」「満足感」など、内発的動機にシフトさせていくのが理想です。 -
親の共感や一緒に喜ぶ時間も“ごほうび”に
「一緒にYouTube見ようか」「ママとゲーム10分やろう」は、物ではないごほうびとして非常に効果的です。 -
ごほうびから“卒業”する意識も持つ
「次はごほうびなしでもできたらすごいね」と、少しずつ“自分の意思でやる”方向に導いていきましょう。
教育経済学から見るごほうびの効果:中室牧子教授の指摘
慶應義塾大学の中室牧子教授は、著書 『学力の経済学』の中で、「ごほうびは行動変容のトリガーとして短期的には効果がある」と述べています。たとえば「勉強したらスタンプがもらえる」といった仕組みは、行動のきっかけにはなるのです。
しかし、中室教授は同時に「ごほうびだけに頼る教育では、将来的な成果にはつながりにくい」とも指摘しています。長期的に重要なのは、自己コントロールや粘り強さといった“非認知能力”。これらはテストでは測れませんが、将来の成功と強く関係する力だと言われています。
つまり、ごほうびは「きっかけ」としては使えるけれど、それだけでは足りないということです。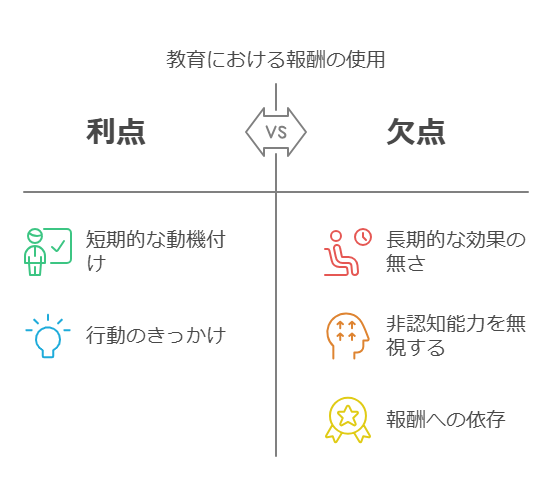
我が家の実例:YouTube=学習時間?ルールはあるけど…
ちなみに、わが家にも「ごほうびルール」はあります。たとえば中学2年の長男には「YouTubeを見る時間=勉強時間」という本人提案のルールがあるのですが、正直あまり守られていません(笑)。
ただこのルール設定、本人が「自分で決めた」というプロセスが大事だったと感じています。親が決めたルールよりも、自分で納得して決めたルールの方が守ろうという気持ちが生まれる。これは先ほどの「自己決定理論」の“自律性”にも通じます。
子ども自身が納得して動けるように、親は「環境」と「きっかけ」を整える役に徹することが、モチベーションの土台づくりにつながっているのかもしれません。
ごほうびに頼らない“内なるやる気”を育てるには?
「やらされる勉強」ではなく、「自分からやりたい!」を育てるには、学習そのものに興味を持てる仕掛けが大切です。
そこで注目したいのが、ワンダーボックスです。
この教材は、好奇心を引き出す仕組みが随所に仕込まれており、「もっとやってみたい!」という気持ちを自然と引き出してくれます。アプリ×キットの両方を使った体験型教材なので、「ごほうびがないとやらない」という状況から、脱却したいご家庭にぴったり。
話題のSTEAM・プログラミング教育教材なら【ワンダーボックス】 ![]()
「Scratchが楽しい」その気持ちを学びにつなげる方法
「10分Scratchをやったらごほうび」──そんな入り口も、悪くはありません。でも、Scratch自体が“楽しいから続けたい”に変わったら、親も子もラクになりますよね。
Codeland(コードランド)は、そんなScratch好きの子にぴったりな、オンラインマンツーマンプログラミングスクール。一人ひとりの個性やペースに合わせてカリキュラムを組んでくれるから、「できた!」という小さな成功体験が、やる気の火を絶やさず灯し続けてくれます。
無料体験もあるので、「うちの子に合うかな?」と気になる方は、ぜひ一度チェックしてみてください。
↓↓ Codelandリンク↓↓
まとめ:ごほうびは“魔法”ではないけど“道具”にはなる
ごほうびは、子どもにとってわかりやすいモチベーションのきっかけになります。でも、目的を見失うような与え方をすると、むしろ自発的なやる気を削ぐ結果にもなりかねません。
だからこそ、親が意識したいのは、「今の行動がどんな成長につながっているか」を伝えること。そして、「ごほうびがなくてもやってみよう」と思える環境を、少しずつ一緒に整えていくことです。
親の言葉、共感、信頼―それも立派なごほうびです。ごほうびを“卒業”することがゴールではなく、「自分で動きたい!」と思える力を育てるための“道具”として、上手に使っていきたいですね。
あわせて読みたい①:①AIが使える子と使われる子:学校が教えてくれない未来格差の話(動機づけ × 教育格差) あわせて読みたい②:みんなやってる?習い事トレンドに惑わされないために(親の判断力テーマ)

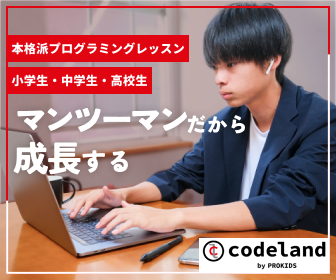
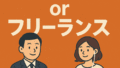
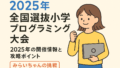
コメント