”子どもにはプログラミング的思考を身につけてほしい」”そう願う親は増えてきました。
でも現実は、なかなか一筋縄ではいきません。
教材を買っても続かないし、スクールも高いし通わせる時間もない。親が教えられるわけでもない……。
そんな中で、「勉強としてじゃなく、日常の中で“しれっと”プログラミングを学ばせることってできないかな」と考える人もいるのでは?
今回は、勉強感ゼロで、しかも無意識のうちに子どもがプログラミング的な思考力を育てられる3つの習慣をご紹介します。
↓↓要約動画(2分11秒)↓↓
1. YouTube動画に“字幕ツッコミ”をつけてみる
まずは、子どもが無意識に見続けているYouTube。 その動画に、テキストで“字幕”や“ツッコミ”をつけて遊ぶだけでも、立派なプログラミング的トレーニングになります。
たとえば、「ここで〇〇って言うの面白いよね」「このタイミングでBGMが変わった」などを文字にして整理してみます。
どこがプログラミング?
- 時間軸とセリフの整合性 ⇒ 順序処理やタイミング制御
- 要約や言い換え ⇒ 情報処理や構造化スキル
“実況動画の構造”を意識すること自体が、アルゴリズムを体で感じる第一歩に。
さらにこの習慣を支える教材としておすすめなのが、シンクシンク。
1日3分で思考力・図形感覚を育てるミニゲーム感覚の教材で、タブレットで“考えるクセ”を身につけるのにぴったりです。
あわせて読みたい:【2025年版】子どもにおすすめ!スクラッチが学べるYouTuber5選
2. ポケモン・マイクラの「攻略メモ」を自作する
子どもが熱中しているポケモン(ポケポケ)やマインクラフト。実はこの「好き」を活かせば、かなりの論理力が育ちます。
おすすめは、タイプ相性表や技の効果、エンチャント(武器に特別効果を付与する)の組み合わせなどを自分でノートにまとめること。
どこがプログラミング?
- 条件分岐(例:水タイプには電気が有利)
- データ構造化(表・分類・ルール設計)
子どもにとっては“趣味の延長”。でも脳内では完全に「if文」と「配列操作」が行われています。
親は「攻略ノート、見せてよ」と声をかけるだけでもOK。学習モードにしないのがコツです。
あわせて読みたい(ポケモンの力はすごい!):『ポケモン』×『スクラッチ』で子どものやる気を自然に引き出す
このような“遊びの延長”でプログラミングを体験できるツールとしては、デジタネもおすすめです。マイクラと連携しながら動画を見て学び、自分で構築する工程が自然と論理力につながります。
↓↓デジタネ公式ページを見る↓↓
【AD】マインクラフトが学びに変わる!?楽しく学ぶ!【デジタネ オンラインコース】3. メルカリやアプリの使い勝手にツッコんでみる
メルカリなどのフリマアプリを使っている中学生も多いですよね。 そのとき、”このボタン見つけにくいな” ”ここに商品が並んでたら便利なのに”と感じたことを言葉にするよう促してみてください。
どこがプログラミング?
- UI/UX(ユーザーインターフェース設計)の視点
- 人がどう使うかを想像する ⇒ 論理設計・デザイン思考
「アプリの設計者って、こういうこと考えてるんだな」と気づいた時点で、その子は“仕組みを作る側”に一歩足を踏み入れたことになります。
この「思考のスイッチ」を自然に入れるサポートをしてくれるのが、ワンダーボックス。
STEAM教育をベースにした教材で、アプリと実物教材が毎月届き、“楽しい”と“考える”をつなぐ仕組みが詰まっています。
↓↓ ワンダーボックス公式サイトを見る↓↓
幼児教育のプロがつくったSTEAM領域の教材【ワンダーボックス】3商材の比較表:子どもの“しれっと学び”を支える教材一覧
| 教材名 | 特徴 | 向いている習慣 | 対象年齢 | 学べる力 |
|---|---|---|---|---|
| シンクシンク | 1日3分の思考力トレーニングアプリ | YouTubeに字幕ツッコミ | 年中~小学生 | 論理的思考・空間認識・集中力 |
| デジタネ | マイクラ×動画教材で学べる | ポケモン・マイクラ攻略メモ | 小学生~中学生 | 条件分岐・データ構造・試行錯誤力 |
| ワンダーボックス | STEAM教材+実物キットの融合 | アプリにツッコむUX視点 | 年中~小学校高学年 | 発想力・構成力・ユーザー視点 |
まとめ:親は“仕掛け”をするだけでいい
ここで紹介した3つの習慣は、どれも「勉強としてやらせる」のではなく、「遊びや日常の中にあることをちょっと意識させる」だけ。
親が「プログラミングやりなさい」と言うよりも、ずっと自然で、ずっと強い学びになります。
無意識のうちに、子どもが“作る側”としての目線を育てていける。
そんな習慣を、今この瞬間から始めてみませんか?
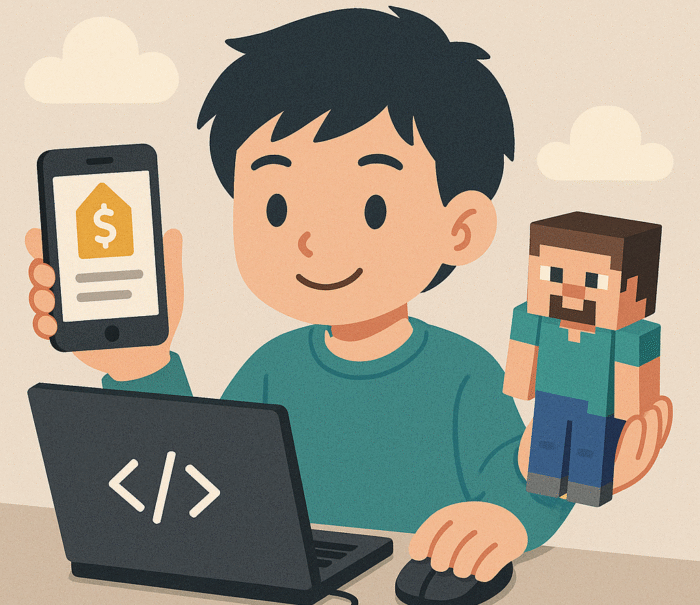

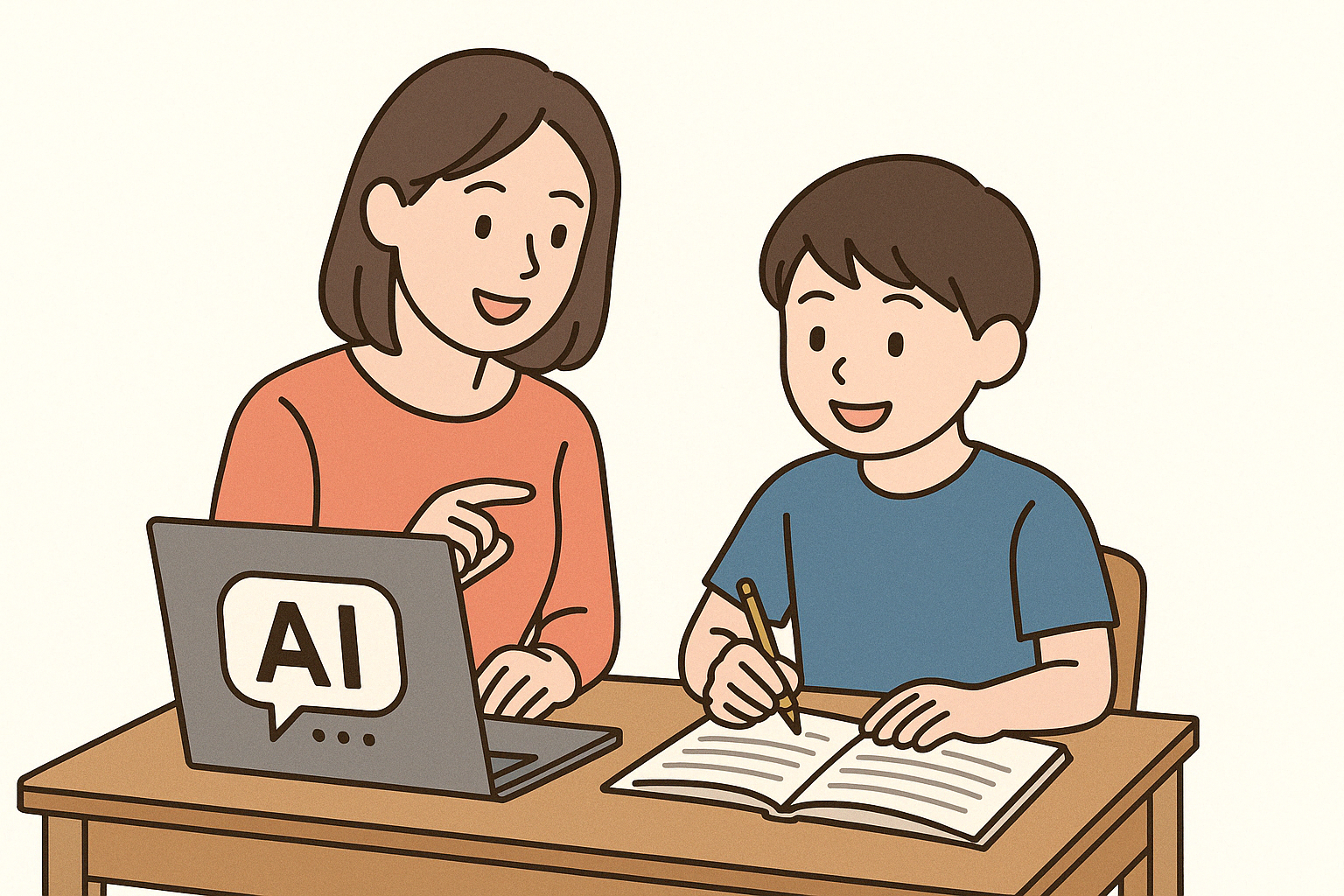
コメント