「AIに仕事が奪われる」。そんな言葉が世間をにぎわせたのは、もう10年近く前のこと。2015年に野村総合研究所(NRI)がオックスフォード大学と共同で発表した調査では、日本の労働人口の49%がAIやロボットによって代替可能と予測されました。
当時、代替されやすい職業として挙げられていたのは、工場作業員、レジ係、清掃員など、いわゆる“ブルーワーカー”の仕事。一方で、知的な判断を伴うホワイトカラー業務は「AIでは代替しづらい」と見られていたのです。
しかし、2025年の今、実際にAIによって効率化・代替が進んでいるのは、むしろホワイトカラーの定型業務。文書作成、表計算、議事録作成、簡易なコード生成など、日常的にオフィスで行われていた業務の多くが、ChatGPTのような生成AIに置き換えられはじめています。
一方で、介護・保育・建設物・物流といった“現場仕事”は、人手不足が深刻化し、「人間にしかできない仕事」として再評価されているのです。
つまり、かつて「真っ先にAIに奪われる」と思われていた職業がむしろ残り、逆に「安泰」とされていた職業が代替されはじめている。この現実が、私たちに新しい教育の必要性を突きつけています。
↓↓要約動画(2分8秒)↓
学校教育では“間に合わない”という不安
2023年以降、ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、教育現場にもその影響が広がりました。しかし多くの公立学校では、生成AIの使用に対して慎重で、「ChatGPTの使用を禁止」する動きが目立っています。
たとえば東京都教育委員会は、都立学校に対して「生成AIを宿題などに使用しないように」という通知を出しました。また、群馬大学では、AIを使って作成されたレポートや論文は「盗用」とみなし、停学や退学といった処分の対象とする方針を示しています。
こうした背景には、以下のような懸念があります。
-
子どもが「自分で考える」ことをしなくなる
-
学習評価の公平性が損なわれる
-
教師がAIツールを正しく指導できるリテラシーを持ちきれていない
このような課題は決して無視できません。しかし同時に、「禁止するだけ」で済ませてよいのか?という疑問も浮かびます。
子どもは純粋だからこそ、“AIで楽をする”誘惑に弱い
私自身も、子どもが「この宿題、ChatGPTで答え出せる?」と聞いてきたとき、戸惑いを覚えました。ChatGPTの出力はそれらしく見えるため、使い慣れた大人でも「考えなくてもいいや」と思ってしまうことがあります。
子どもたちは、そんな誘惑に対して防御力が高くはありません。
良くも悪くも素直で、「便利=使っていい」とすぐ結びつけてしまうからです。
だからこそ、私たち大人は「AIの正しい使い方」だけでなく、「どう付き合うか」という“姿勢”を伝える必要があると強く感じています。
私の夫(地方公務員)は仕事で利用する生成AIについて、職場での活用状況(約10%の人が利用)とか注意点(個人情報は入力しない)などを子どもたちに話していますが、これもAIとの付き合い方の一つだと思います。夫は法律・省令の解釈を一瞬で出してくれるChatGPTの威力に驚くと同時に法律作成にAIが絡めば公務員の残業時間(特に霞が関の官僚)が大きく減ると期待していました。
AIは“考える道具”にも、“ズルする道具”にもなる
生成AIは、使い方次第で学びを広げる「思考のパートナー」にもなれば、安易に答えを得てしまう「思考停止装置」にもなり得ます。
たとえば、次のような使い方であれば、AIは学びの質を高める強力なツールになります。
- 作文や読書感想文の構成を一緒に考える
- ScratchのゲームアイデアをAIに相談する
- 理科の自由研究のテーマや進め方のアイデアをもらう
-
歴史の出来事について複数の解釈を聞き、比較する
そして、親として次のような声かけを意識すれば、AIは“答えを出す道具”から“考えるきっかけ”に変わります。
「この答え、あなたはどう思う?」
「他の視点もあるんじゃない?」
「本当に正しい?他でも調べてみよう」
AIに全てを任せるのではなく、AIと一緒に考えるというスタンスを育てることが、今後ますます重要になっていくでしょう。
プログラミングを楽しく学習するには・・・⇒『ポケモン』×『スクラッチ』で子どものやる気を自然に引き出す
家庭こそが“AIリテラシー教育”の主戦場になる
学校が慎重な立場を取っているからこそ、家庭での関わり方が重要になります。
特別なプログラミングスキルやIT知識は不要です。親が子どもと一緒に“学ぶ姿勢”を見せるだけで、大きな教育効果があります。
たとえば、
- ChatGPTを一緒に触って「どこまでがOKか」を話し合う
- 自由研究や創作活動でAIを使い、「使ってよかったこと/不便だったこと」を共有
- 出力された内容の正確性を一緒に検証する
-
「AIと意見が違ったらどうする?」と話す
これらの体験を積むことで、子どもたちは自然と「AIに使われる人」ではなく、「AIを使いこなす人」になっていきます。
AI時代に求められるのは“使える力”より“向き合える力”
これからの子どもたちは、AIが当たり前に存在する世界で生きていきます。AIをどう活かすか、どこまで頼るか、どう判断するか─その力こそが、これからの時代に求められる“人間力”です。
学校教育がそこに追いつくには、まだ時間がかかるでしょう。だからこそ、今、家庭ができることはたくさんあります。
ChatGPTが悪者なのではありません。
それをどう使うか、子どもにどう渡すかが、私たち大人に問われているのです。
AIは、子どもに“思考停止”を与える道具にも“思考の翼”を与える道具にもなります。
分かれ道は、今、ここにあります。
小学生から楽しく学べる【テックキッズスクールジュニア】
プログラミングを楽しく、わかりやすく学びたい小学生におすすめなのが、テックキッズスクールジュニアです。Scratchを使ったゲーム制作を通して、自然にプログラミング的思考が身につくカリキュラムが特徴。
初めてでも安心して参加できる無料体験授業も実施しているので、まずは雰囲気を確かめてみるのがおすすめです
中高生の本格チャレンジに【Life is Tech(ライフイズテック)】
さらにステップアップしたいなら、Life is Tech(ライフイズテック)も注目です。
アプリ開発、デザイン、AIなど、将来につながる本格的なITスキルを学ぶことができます。
自分のアイデアを形にしたい、もっと深く学びたい、そんな意欲を後押ししてくれるスクールです。こちらも無料体験が可能です。
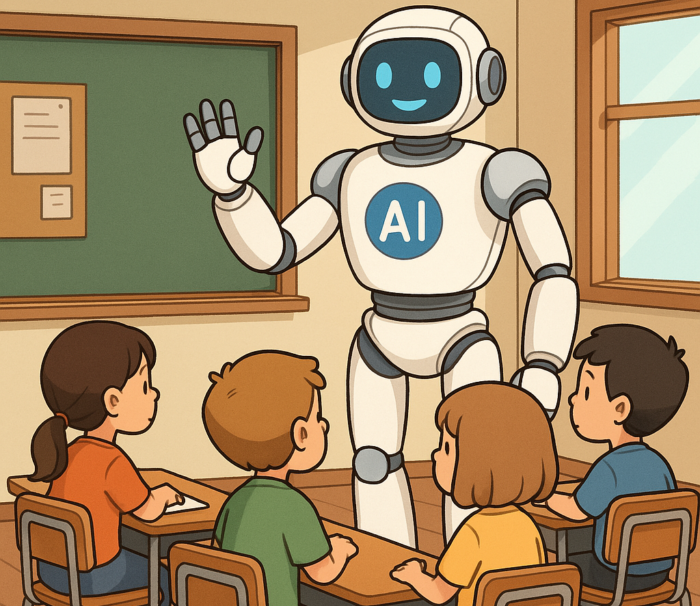

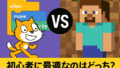
コメント